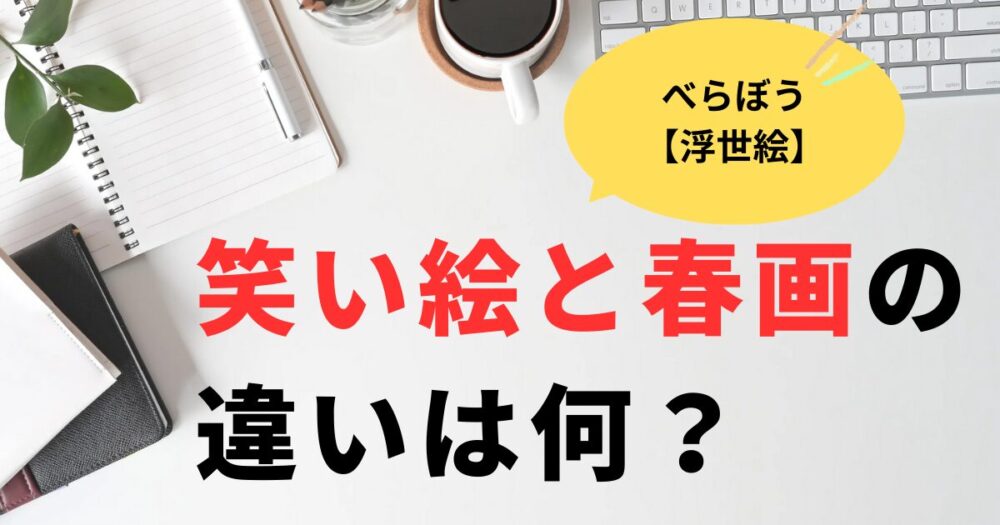大河ドラマ「べらぼう」も終盤に差し掛かってきましたね!
ドラマ内で出てきた「笑い絵」って言葉初めて知った人が多いのではないでしょうか?
あまり現代では聞き馴染みのない単語なので、「笑い絵ってどんな絵?」「春画とは違うの?」という疑問があるのはないかと気になりました。
今回は【べらぼう】笑い絵と春画の違いは何?江戸時代の別称と隠語!について見ていきましょう!
【べらぼう】笑い絵と春画の違いは何?別称と隠語!
NHK大河ドラマ『べらぼう』で登場する「笑い絵」と「春画」は、
基本的には同じもの
ですが、それぞれの名称の使われていた時代が異なります。
・「笑い絵」はユーモアを強調した江戸時代の浮世絵の隠語
・「春画」は明治以降に定着した「笑い絵全般」の浮世絵の呼び方
という違いがあります。
 もちうさ
もちうさドラマべらぼうは江戸時代だね
時代によって呼び名が変化したんですね!
それぞれの内容はそんなにちがうのでしょうか?
笑い絵

「笑い絵」とは、江戸時代における
男女のイチャイチャを題材にしたポップな浮世絵の一種
を指していて、当時の庶民の間で広く親しまれた娯楽的な作品群を意味します。
ユーモアや風刺を交えた明るい表現が多く、絵草紙屋の店頭に公然と並べられて売られていたそうです。
 もちうさ
もちうさいやらしい感じではないね
性的な内容を直接的に言及せずに「笑いを誘う絵」として親しみを込めて表現されていました。
喜多川歌麿をはじめとする著名な浮世絵師が手がけ、蔦屋重三郎が版元として関わったものも少なくありません。
ドラマでは、規制との闘いや文化的意義を強調する描かれ方をしています。
春画
「春画」という呼称は
明治時代以降に定着した呼び方で、直接的な表現を含む浮世絵
のことを指していました。
 もちうさ
もちうさ今で言う青年誌的なものかな
 うさめがね
うさめがね親に見つからないように部屋に隠すやつ?
厳密に「笑い絵」を「人を笑わせるこっけいな絵」の総称として使う場合もありますが、
歴史的な文脈では春画を指すことがほとんどです。
隠語

江戸時代には「笑い絵」の他、
「枕絵」「艶本」「わ印」
などと呼ばれていました。
 もちうさ
もちうさお肉の隠語とおなじ感じだね
 うさめがね
うさめがね鶏肉「かしわ」、馬肉「さくら」、猪肉「ぼたん」みなたいな?
国から禁止される中、庶民がひっそりと娯楽を楽しむ為に産み出された知恵です。
ドラマでは、この「笑い絵」の制作過程を通じて江戸の自由な文化や検閲・規制との闘いが描かれているんですね!
蔦重さんはメディア文化をめぐる戦いを経て、世の中に庶民の娯楽を広める挑戦をした人物と言えます!
まとめ
今回は【べらぼう】笑い絵と春画の違いは何?江戸時代の別称と隠語を解説!について調べてみました!
現代のメディアの基礎を築いた蔦重さんの挑戦のおかげで私達は様々な形で楽しむことができているんですね。